 . . |
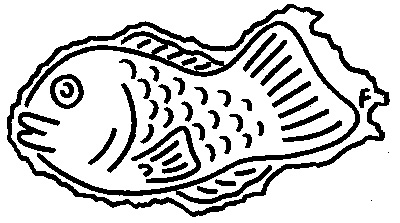
|
.
|
|
.
|
| ●街へ、ふらりと買い物に出た。冬ざれの乾いた空気が肌を刺す、去年のちょうど今頃のこと。何のお祭りか、小広場に近郷の物産を並べた屋台が犇めいて、自分の意志で進めぬ程人集りしていた。味噌、醤油、漬物の類いに可成りそそられたけれど、自重して(買わずに)立ち去ることにした。押されて蹌踉けた処がたい焼き屋の前。拍子でひょいと伸びた掌にたい焼きが一尾……そんなわきゃないけれど、ともかく儂はその一尾を得た。倅んだ指先にたい焼きの温もりが心地よかった。懐に仕舞った。体中にほんのりと……。 ▲たい焼きを手土産に仕事場に現れた客人があった。何でこんなものを……と、若かった儂は半ば呆れ、鳩尾を叩きながらやっとこさ一尾だけ片付けた。その頃はまだ餡の類いを受け付けぬ胃袋だった。有名な「ヤマカジ対アンツルの〈たい焼きの尻尾まで餡があるべきか否か〉論争」は、彼の客人から教えられた。 ■年月を経て、ある日人形町のたい焼き屋の前を通りかかった。白衣のおっさんが、植木鋏みたいな形のたい焼き器を、ガランゴロンと大袈裟な振りで火の上に転がしていた。大喜びする連れに付き合って、苦笑しながら二尾目のたい焼きを食った。あの頃、〈およげたいやきくん〉というやつが流行っていたのかも知れない。そして今回が、儂にとっての三尾目のたい焼きとなった。「ムフフフフ……旨いじゃん」と呟いた。いつの間にかこういうものも受け入れる胃袋になっていたのだ。数か月前に、たい焼きの“魚拓”を採って歩く変人(宮嶋康彦氏)の本に出合った。そんな本を見て大喜びしている儂も、やっぱり変な人なのかしら――。 |
|
. |
Copyright (C) 2002-2003 idea.co. All rights reserved.